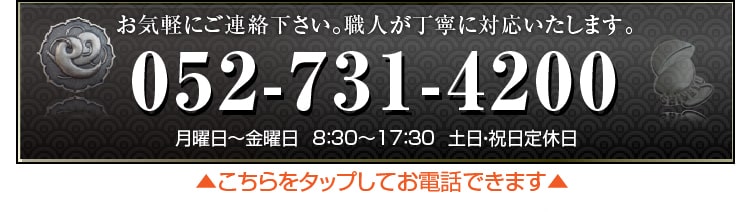








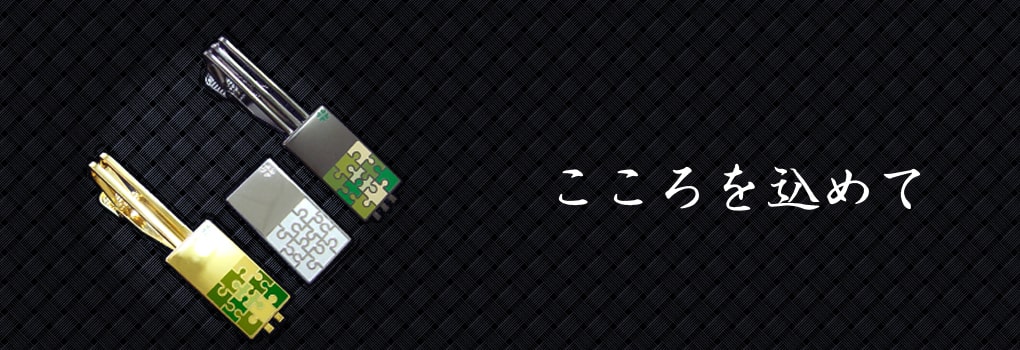


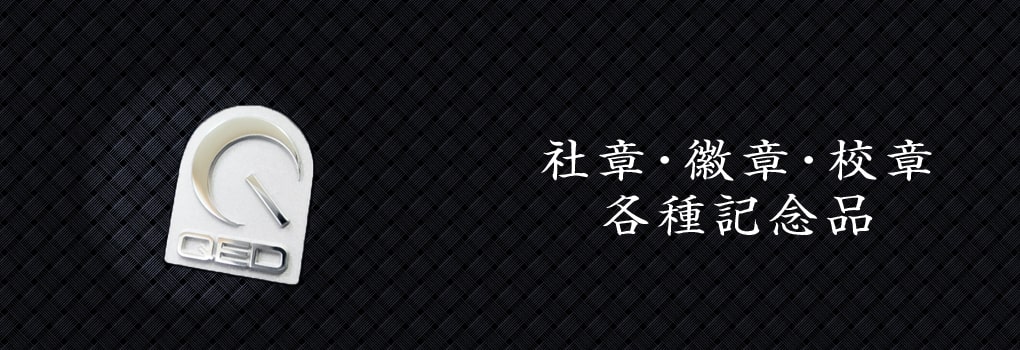
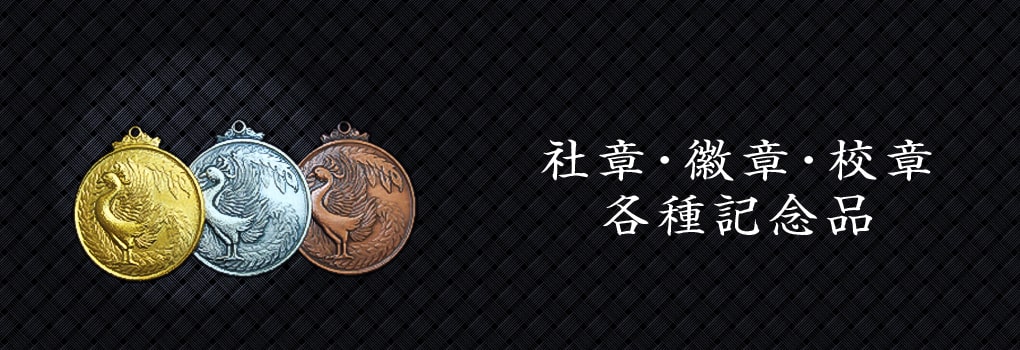
社章 TOP > 家紋

家紋は家の重要な象徴として極めて神聖なものとされてきました。 祖先を崇拝し、家名をことのほか大切にする日本の文化の中で家紋の果たす役割は大きいものです。 日本に存在する家紋の数は4000以上といわれています。 家紋は大きく分けて7種類あり、『植物紋』『動物紋』『器具紋』『建造物紋』『天文地理紋』『文様紋』『文字紋』があります。 その中のいくつかを製造させていただく機会がございましたのでご紹介させていただきます。 (参考資料 『日本の家紋』 著者 進士慶幹 加藤秀幸)

【桐紋】(植物紋)
白桐の花・花梗と葉とを組み合わせた紋です。
聖帝が世に出るのを待って姿を見せる鳳凰の宿る木が桐であるという中国の万葉集ともいえる詩経にもその名が現れ、日本でも平安時代に愛唱された『白氏文集』にも見られます。
平安・鎌倉時代に、竹・鳳凰・麒麟と組み合わされて、衣服の織文として用いられ、12世紀ごろには、天皇の黄櫨染ほうの文様に織られるようになりました。
皇室の紋章となったのは、菊紋と同じころからと考えられています。(参考資料 『日本の家紋』 著者 進士慶幹 加藤秀幸)

【鷹羽紋】(動物紋))
白桐の花・花梗と葉とを組み合わせた紋です。
聖帝が世に出るのを待って姿を見せる鳳凰の宿る木が桐であるという中国の万葉集ともいえる詩経にもその名が現れ、日本でも平安時代に愛唱された『白氏文集』にも見られます。
平安・鎌倉時代に、竹・鳳凰・麒麟と組み合わされて、衣服の織文として用いられ、12世紀ごろには、天皇の黄櫨染ほうの文様に織られるようになりました。
皇室の紋章となったのは、菊紋と同じころからと考えられています。(参考資料 『日本の家紋』 著者 進士慶幹 加藤秀幸)

【巴紋】(文様紋)
十字・クロス・卍などとともに、この勾玉のような形は、古くから、由来のはっきりしないままに、人間の精神面に深く根を下ろしています。
巴紋は、水の渦巻いた形とみられたため、防火の祈りをこめて、平安時代末期から、鐙瓦の文様に用いられるようになり、調度品や車輿・衣服の文様としても、平安末期から鎌倉時代にかけて流行し、木曾義仲の愛妾といわれる巴御前の名は、この文様を好んで用いたところからつけられたそうです。(参考資料 『日本の家紋』 著者 進士慶幹 加藤秀幸)

【木瓜紋(もっこうもん)】(文様紋)
木瓜というのは、御簾の周囲に廻らした布帛、『帽額』にある文様が独立したもので、植物の木瓜はあとからつけられた名だそうです。また、木瓜(ぼけ)
や胡瓜の切り口を図案化したというのも誤りです。これらも中国伝来の文様で、唐代には官服の文様となったものであるが、
これを徳大寺実能が車の文様に用い、その後、徳大寺公清が衣服の文様とし、次第に家の文様となっていったそうです。(参考資料 『日本の家紋』 著者 進士慶幹 加藤秀幸)

【桔梗紋】(植物紋)
秋の七種のひとつに数えられる桔梗は、『太平記』に土岐市の一族、武士団の象徴として姿を表しました。
『土岐の桔梗一揆、水色の旗をさして』というように、桔梗を目印にした集団が生まれたのです。また、明徳三年の『相国寺供養期』には、将軍義満の後陣の随兵五番の土岐頼益が、直垂に桔梗紋をつけていたことが記されています。
天正十年、本能寺の変で、主君織田信長を討った明智光秀の紋が桔梗であったことはあまりにも有名です。
尚、サンプル画像は『坂本龍馬』の家紋だと言われております。
(参考資料 『日本の家紋』 著者 進士慶幹 加藤秀幸)

【橘紋】(植物紋)
奈良県尼ヶ辻町にある第十一代垂仁天皇陵の周濠の東に島がある。
これが田道間守の墓と伝えられる。
彼は勅命を受けて不老長寿の薬を求めて中国に渡り、『ときじくのかぐのこのみ』をもって帰国したが、これが橘の実であったという。
家紋としては藤原姓に関係のあった家に多い。
俗説によると日蓮の紋もこれという。
最も多く用いられたのは一橘で、そのほか二、三橘や花橘、実と三葉を真上から描いた向橘などがある。(参考資料 『日本の家紋』 著者 辻合喜代太郎)

【菊紋】(植物紋)
菊の花は平安時代に中国から渡来したいわゆる舶来の珍しい花であった。
中国では、その花の姿、香の気高いことから四君子の一つとして人々に愛されていた。
九月九日は重陽の節句として菊花の酒を汲んで延命長寿を祈ったという。
このことから菊は延年草ともいい、また、花を太陽に例えて日精、日章とも称し、百草の王とされた。
そんなわけで菊紋は皇室の紋とされ、皇族の紋はいずれも菊花の表現を少しずつ変えて用いられている。
菊紋には花の表し方によって単弁、複弁、描き菊、割菊、また、葉と花の組み合わせやほかの紋との組み合わせなど種類が多い。(参考資料 『日本の家紋』 著者 辻合喜代太郎)

【イ菱】
歌舞伎の成駒家が使用している家紋として有名です。

貴族文化の栄えた藤原時代には和風化された優雅な文様が、それぞれ自己の趣味によって選ばれ、衣服や調度品、輿車などに使用された。
これらの文様は、はじめはもちろん装飾ということが目的であったであろうが、いつの間にか家の標識とされるようになり、使用者も次第に意識的にこれを用いるようになった。そして、この文様が家という制度と結合して家紋が誕生したものである。
この家紋の生まれた背景は、古来より多くの研究者によって解明されようとしているが、なかなか困難なことである。この分野で最高の権威者である故沼田頼輔氏の『日本の紋章学』という著書が学術参考書としては最適であろう。
家紋の起源に関するほかの記述として、山鹿素行は『武家事記』に、《家紋は聖徳太子の時に旗印として、また武家では源頼朝の時に既に始まっている》と述べている。
新井白石は『紳書』に《公家の家紋は公家の車の文様から転化されたものであろう》と記している。
また、生田目経徳は『家紋の由来』において、そのはじまりには上古の品部制度の頃として、品部制度に家紋の始まりを見出そうと試みている。これらの文献を通して言えることは、もともと家紋の起こりは公家と武家とで異なったということである。
公家社会での起こりには、平安のころから装飾をも兼ねていた自家用の車の文様からの転化、または衣服の文様からの転化、記念的な意義に因んでとくに定めたもの、という三つの経過があげられる。
公家の車に文様をつけて装飾したことは諸書に明らかである。これは院政のころから鎌倉頃にかけて順次用いられ、単に装飾の目的でつけられた文様がしだいに家紋に転化したのである。
一方、武家の場合は幾多の戦場において見方を識別する目的、および武勲を明白にするための旗印や馬印が必然的に要求され、さらに家門の団結を企てるための象徴としてこれを用いるようになったと思われる。
従って、そのためには家紋は単純でしかも鮮明な図形であるほうが都合よく、一、二、三、●、○、三ツ星のような単純な図形がその目的にかなったのである。
(参考資料 『日本の家紋』 著者 辻合喜代太郎)

一部例 ※クリックすると拡大画像が表示されます。